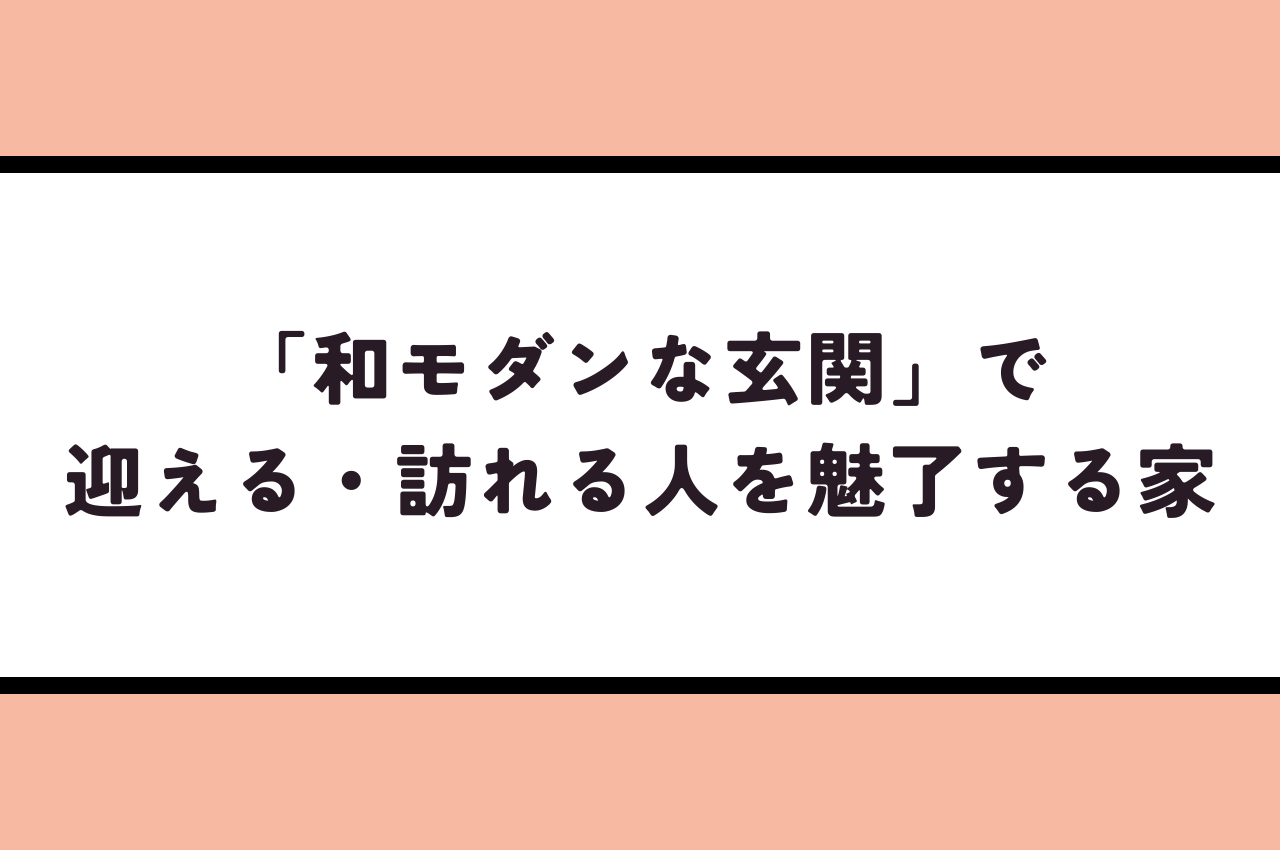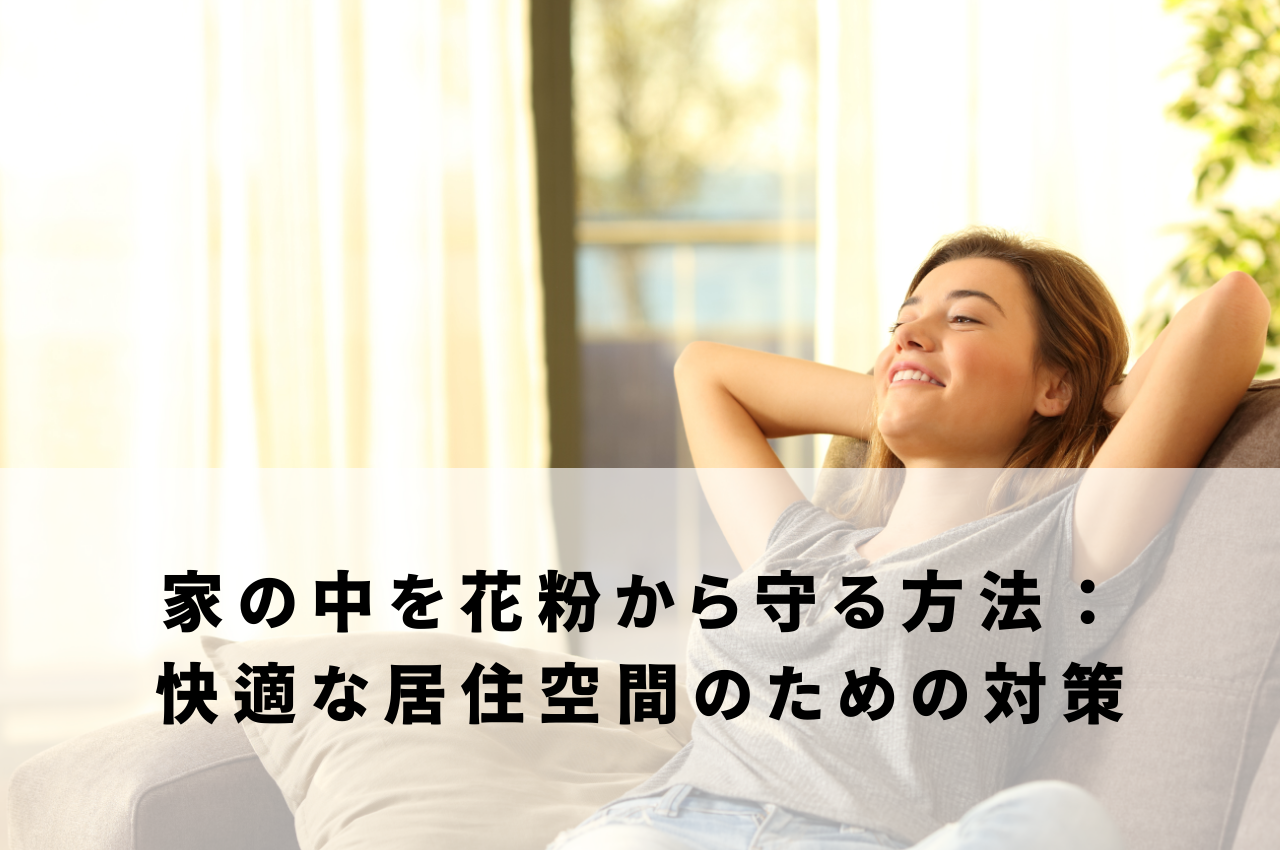注文住宅を検討されている方へ向けて自然素材の魅力をご紹介します!
|日記
注文住宅を検討されている方で、自然素材の家に憧れている方も多いのではないでしょうか。
自然素材の家にはさまざまな魅力があります。
そこで今回は、松本市にお住まいの方へ自然素材の家にするメリットと従来の家との違いを紹介します。
ぜひ参考にしてください。
□自然素材の家にするメリットをご紹介!
ここでは自然素材のメリットを4つのポイントに分けて説明します。
1つ目は化学物質が少ない点です。
自然素材では接着剤やコーティングを使用しないため、化学物質の含有量が少ないです。
そのため、小さなお子様やペット、体の弱い方がいるご家庭でも、安心して暮らせるでしょう。
2つ目は耐久性が高い点です。
多くの自然素材は耐久性が高い傾向にあるため、手入れをすることで長く使用できます。
合板フローリングの場合、30年前後で接着剤が剥がれて弱ってきます。
一方で、自然素材を使用した無垢フローリングでは剥がれる心配もなく、傷がついてもヤスリをかけることできれいになります。
3つ目は触り心地が良い点です。
素足や素手で触れる機会が多いフローリングやカウンターに無垢材を採用することで、優しい触り心地になります。
工業製品によく見られる、ヒヤッとした冷たさや湿気でべたつくこともありません。
4つ目は気持ち良い空気を作ってくれる点です。
無垢材や珪藻土などの自然素材は、湿度を一定に保つ働きがあるため、室内で快適に過ごせます。
雨の日には湿気を吸い込み、晴れた日に吐き出すことで気持ちの良い環境を作ってくれます。
□自然素材の家と従来の家の違いをご紹介!
これから自然素材の家と従来の家の違いについて、3つのポイントに分けて説明します。
1つ目は住み心地です。
土を使用した壁や木の床など、自然の家は従来の家に比べて住み心地が違うという意見が多いです。
自然素材の家は、室内の温度や湿度を調整する働きがあるため、季節を問わず過ごしやすいのが魅力の1つでしょう。
2つ目はメンテナンスです。
従来の家にそれぞれのメンテナンス方法があるように、自然素材の家でも適切なメンテナンス方法があります。
自然素材の家は長持ちするので、日々のメンテナンスは必要ですが大きなメンテナンスをあまり必要としません。
3つ目はコストです。
自然素材の家は、従来の家に比べるとコストがかかる傾向にあります。
理由としては、オプションとして追加料金が発生しやすいことが挙げられます。
オプションの内容は自分で選べるので、工夫すれば安く済ませられる可能性があります。
また、初期費用は高くなっても、維持費に関しては自然素材の家の方がかからないこともあります。
□まとめ
この記事では、松本市にお住まいの方へ、自然素材の家にするメリットと従来の家との違いについて紹介しました。
今回の内容を通して、自然素材の持つ魅力を知っていただければ幸いです。
注文住宅に関してお悩みやご相談のある方は、お気軽に当社にお問い合わせください。
注文住宅で後悔しないために!照明で気を付けたいポイントについてご紹介します!
|日記
注文住宅の内装を考える上で、照明をどうするか悩まれる方も多いのではないでしょうか。
照明選びで後悔しないためには、事前に適切な照明を調べておくことが大切です。
そこで今回は、ダウンライトについてと照明で後悔したポイントを紹介します。
木曽市にお住まいの方はぜひ参考にしてください。
□ダウンライトについてご紹介!
ダウンライトは何かご存じの方も少ないと思います。
ここではダウンライトの定義について説明します。
まず、ダウンライトには、室内全体を照らすシーリングとは違い、スポットライトの様に明かりを1カ所に集中して照らす働きがあります。
そのため、部屋を広く見せたい方や、天井を高く見せたい方におすすめの照明です。
また、存在感をなくして部屋全体をシンプルにまとめたい方にもぴったりです。
ダウンライトは天井に穴をあけて埋め込むLED照明です。
種類はベースタイプ、ユニバーサルタイプ、ピンホールタイプの3つに大きく分けられます。
ベースタイプは、角度の調整ができませんが、ユニバーサルタイプでは向きを変えられます。
また、ピンホールタイプでは飾り棚でよく見られるタイプで、目立たせたいインテリアをピンポイントで照らしてくれます。
次に、ダウンライトには天井埋め込み式と交換タイプがあります。
ダウンライトを採用した場合のLEDの光源寿命は約40000時間です。
天井埋め込み式の場合、LEDが切れると器具ごと交換する必要があります。
交換の際は、電気工事士の資格を持った会社に依頼しなければならないため、注意しましょう。
□照明で後悔したポイントをご紹介!
続いて照明で後悔した理由やポイントについて説明します。
後悔した理由として多いのが照明の調光と調色に関する問題です。
調光機能を付けない部屋があると、夜中や朝方の活動に支障をきたす可能性があります。
少しだけ照明をつけたい時にも、調光機能がないと明るすぎる部屋になってしまいます。
調色機能を備えると、ダウンライトの光の色を変えられます。
例えば、落ち着いた雰囲気にしたい時はオレンジ、書いたり読んだりする時はホワイトにするなどシーンによって調節が可能です。
使用頻度の多い部屋に関しては調光や調色機能を設けることがおすすめです。
特に、リビングをさまざまな用途で使用する予定の方は、多くのメリットを得られるでしょう。
□まとめ
今回の記事では、ダウンライトについてと照明で後悔したポイントについて紹介しました。
注文住宅の内装を考える上で照明をどうするか悩まれている方は、今回の記事を参考にしていただければ幸いです。
木曽市在住で、注文住宅に関して疑問や相談のある方は、当社にお問い合わせください。
注文住宅を検討されている方へリビングの間取りで注意すべきポイントをご紹介します!
|日記
注文住宅を建てる上で、リビングの間取りをどうするのか悩まれる方も多いのではないでしょうか。
後悔しないリビングに仕上げるために押さえておきたいポイントがいくつかあります。
この記事では木曽市にお住まいの方へ、リビングづくりで後悔しないためのポイントと開放感のある間取りに仕上げるためのコツを紹介します。
□リビングづくりで後悔しないためのポイントをご紹介!
まずは、リビングづくりで後悔しないためのポイントを4つに分けて説明します。
1つ目は動線を考えることです。
生活の拠点となるリビングでは、生活動線や家事動線に配慮しながら間取りを考えることが大切です。
リビング内はもちろん、リビングに隣接する洗面所やトイレといった場所の間取りも考えながら進めましょう。
2つ目はあらかじめ収納を設けることです。
家族間で使用する日用品や雑誌、子供のおもちゃなどでリビングが散らかりがちです。
散らかりやすい要因として、収納が少ないことも考えられます。
そのため、適切な量の収納設備を設けておくことで、きれいな状態を保ちやすくなるでしょう。
3つ目はコンセントの数と位置に気を付けることです。
生活の注意となる場所ではコンセントを多く設置しておくことが大切です。
コンセントが家具の裏に位置していると、使用できないことがあるので注意しましょう。
4つ目は家具や家電の配置を考えることです。
家具や家電の大きさ、配置も間取りを考える上で大切です。
事前に設置した際に、不都合が起きないかどうかの計算をしておきましょう。
□開放感のある間取りに仕上げるためのコツをご紹介!
これからリビングをおしゃれに演出するためのコツを4つに分けて説明します。
1つ目は天井の高さを変えることです。
例えば、リビングの天井だけを少し高くして開放感を感じさせ、段差部分のカラーを変えてアクセントを加えると良いでしょう。
また、天井を上げて梁をあえて見せるウッド調のアクセントもおすすめです。
2つ目は生活感を見せないことです。
実際に暮らし始めてから、物が多くてまとまりがなくなるケースも少なくありません。
おしゃれな空間を維持するためには、見せるものと見せない物を分けることが大切です。
3つ目は照明を工夫することです。
照明は、部屋をおしゃれに見せるために欠かせない要素の1つです。
吹き抜けのリビングであれば、壁付けのスポットライトを配置することで、落ち着いた空間に仕上がるでしょう。
4つ目はデザインやカラーの統一感を出すことです。
全体のテイストを決めて、方向性を確認することが大切です。
一つ一つがおしゃれでも、組み合わせ方によって残念な印象になることがあるので注意しましょう。
□まとめ
今回の記事は、木曽市にお住まいの方へ、リビングづくりで後悔しないためのポイントと開放感のある間取りに仕上げるためのコツを紹介しました。
リビングづくりで後悔しないためにも間取りに注意しながら進めるようにしましょう。
リビングづくりをする際は、今回の内容を参考にして役立てていただければ幸いです。
別荘が寒い場合に取り入れたい断熱リフォームについてご紹介します!
|日記
塩尻市にお住まいで、別荘の断熱リフォームについてお考えの方はいらっしゃいますか。
別荘で快適に過ごすためには、寒さ対策はしておきたいものです。
そこで今回は別荘が寒い場合に取り入れたい窓の断熱リフォームと、断熱リフォームのポイントについて紹介します。
ぜひ参考にしてください。
□窓の断熱リフォームについてご紹介!
まずは、窓の断熱リフォームで行う4つの方法について説明します。
1つ目は窓の交換です。
既存の枠ごと取り除いて、新しい枠とペアガラスなどの障子を取り付ける工事です。
枠ごと取り除くので隙間が生まれる心配もなく、さらに断熱性能を高められます。
しかし、時間と費用がかかる点がデメリットとして挙げられます。
2つ目は障子交換です。
建物本体はいじらずに交換するため、短時間で完了し、費用も抑えられます。
障子のフレーム部分のみを断熱性能の高いものに変えられます。
3つ目はガラス交換です。
障子のフレームから既存のガラスを取り除いて、ガラスのみを交換する方法です。
障子交換と同様に、部分工事となるため時間や費用をかけずに工事できます。
既存の枠がアルミサッシの場合は、枠部分に結露が発生することがあるので注意しましょう。
4つ目は内窓設置工事です。
現在ある窓の室内側に、もう1つ窓を設ける方法です。
二重窓の機能を果たし、樹脂製の窓を取り付けることでより高い断熱性期待できます。
カラーも既存のものに合わせられるので、まとまりのない見た目になることもありません。
□断熱リフォームをする際のポイントをご紹介!
ここでは断熱リフォームをする際に知っておくべきポイントを紹介します。
まず、家の中から熱が逃げる際に、多くの割合を占めているのが窓です。
全体を10割とした際に、窓などの開口部から熱が逃げる割合は5割程度と言われています。
そのため、断熱性能を高めたい時の優先順位としては窓の断熱リフォームがおすすめです。
断熱性能の高い窓に交換するだけで、室内の断熱性能がぐんと上がります。
また、単板ガラス窓から複層ガラスに変えることで断熱効果が期待できます。
複層ガラスといっても種類はさまざまなので、自分にあった断熱性能のものを選ぶようにしましょう。
□まとめ
今回の記事では別荘が寒い場合に取り入れたい窓の断熱リフォームと断熱リフォームのポイントについて紹介しました。
快適な環境で過ごすためにも、断熱リフォームを検討してみてはいかがでしょうか。
塩尻市にお住まいで、別荘の断熱リフォームに興味のある方はお気軽に当社にお問い合わせください。
別荘のリフォームを検討中の方へ!注意点を把握しておきましょう!
|日記
「別荘が劣化していたのでリフォームしたい」
「別荘をリフォームする際の注意点を知りたい」
別荘のリフォームを検討中の方で、このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、別荘のリフォームを検討中の方に向けて別荘をリフォームする際の注意点についてご紹介します。
□別荘の老朽化について
皆さんは、別荘の老朽化が早いことをご存じでしょうか。
実は別荘は、一般的な住宅よりも老朽化が早いと言われています。
なぜなら、別荘は換気されない状態が続きやすいからです。
頻繁に別荘を使っている方は問題ないかもしれませんが、使用頻度が低いと換気が行われず、ほこりがたまってしまいます。
また、周囲の環境による影響も大きいです。
特に自然豊かな場所に別荘を購入されている方は、頻繁に雨や風による影響を受けています。
これらの影響により、別荘の老朽化が早くなってしまうのです。
そのため、定期的にメンテナンスやリフォームを行うことをおすすめします。
□別荘をリフォームする際の注意点
ここからは別荘をリフォームする際の注意点として3つのポイントをご紹介します。
*設備の古さ
1つ目は設備の古さです。
別荘を頻繁に使わない方は、定期的に設備が劣化していないか確認しておくことが重要です。
特に別荘では周囲の環境による影響が大きいので、必要な場合にはリフォームを検討する必要があります。
*気候に合わせる
2つ目は気候に合わせることです。
別荘を建てた場所では、季節によっては厳しい自然環境であることも多いはずです。
そのため、季節による影響も考慮したうえで、リフォームのプランを考えましょう。
特に、内装に関してはどの季節でも快適に暮らせるような工夫が必要です。
リフォームで失敗しないためにも、別荘を建てた場所の周辺環境や気候を確認して的確な対策を取り入れることが重要です。
*別荘購入の目的に合わせる
3つ目は別荘購入の目的に合わせることです。
別荘を購入された際に、明確な目的を持っている方が多いと思います。
別荘をリフォームされる場合は、その目的に合わせたプランを考えましょう。
例えば、お子様とゆっくり過ごすための別荘を実現するのであれば、子育ての環境やお子様が安全に遊べる環境を取り入れたプランを計画しましょう。
□まとめ
今回は別荘のリフォームを検討中の方に向けて別荘をリフォームする際の注意点についてご紹介しました。
別荘をリフォームする際の注意点について理解していただけましたか。
塩尻市でリフォームを検討中の方は、ぜひ当社までご相談ください。
当社の専門家が皆様を全力でサポートいたします。
注文住宅の外観でお悩みの方へ!外観の決め方を解説します!
|日記
「注文住宅を建築するうえで外観について悩んでいる」
「注文住宅の外観の決め方について教えてほしい」
注文住宅の建築を検討中の方は、外観について悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、注文住宅における外観の決め方についてご紹介します。
□注文住宅を外観の決め方
では早速、注文住宅の外観の決め方について見ていきましょう。
ここでは3つのポイントについてご紹介します。
*単色に統一する
1つ目は単色に統一することです。
外観に関わる要素の中でも、住宅の色について悩んでいる方も多いはずです。
外観の色を選ぶ際は、単色に統一することを意識しましょう。
複数の色を使いたいという方は、2色までにまとめることをおすすめします。
あまり多くの色を使いすぎてしまうと、外観の統一感がなくなり印象も悪くなってしまいます。
また、2つの色を使いたい方は、調和しやすい色を選びましょう。
*外観のデザインイメージを絞る
2つ目は外観のデザインイメージを絞ることです。
外観にも和風や洋風などのデザインイメージがあります。
デザインイメージが変わることで、外観の印象も大きく変わります。
そのため、あらかじめ外観のデザインイメージを絞っておくことが重要です。
*形状を決める
3つ目は形状を決めることです。
住宅の形状も外観に関わる重要な要素の1つです。
形状を決める際は、窓の種類や位置を確認しながら進めましょう。
これら3つのポイントに注意しながら、統一感のある外観にすることを目指しましょう。
□注文住宅で外観を選ぶ際の注意点
ここからは外観を選ぶ際の注意点について確認しておきましょう。
注文住宅で外観を選ぶ際には、メンテナンスについて考慮しておくことが重要です。
どの素材を選んだとしても、定期的なメンテナンスが必要です。
そして、素材ごとにメンテナンスの規模や費用も異なります。
住宅の印象を良くするためにも、外観のデザイン性は重要な要素です。
しかし、デザイン性だけを重視しすぎると後悔するかもしれません。
そのため、注文住宅の外観を選ぶ際はデザイン性だけで選ぶのではなく、メンテナンスのしやすさも考慮しておきましょう。
そして、何より自分の生活スタイルと照らし合わせながら自分に合ったものを選びましょう。
□まとめ
今回は注文住宅における外観の決め方についてご紹介しました。
外観の決め方について理解していただけましたか。
ご不明な点がある方は、ぜひ当社にお問い合わせください。
木曽を中心に当社の専門家が皆様を全力でサポートいたします。
防音室のメリットとは?注文住宅で防音室を作りたい方は必見!
|日記
「注文住宅に防音室を作ろうと考えている」
「防音室を作るうえでメリットや注意点について教えてほしい」
注文住宅に防音室を作りたいという方も多いでしょう。
そこで今回は、注文住宅に防音室を作るメリットと注意点についてご紹介します。
□注文住宅に防音室を作るメリット
まずは、防音室を作るメリットについてご紹介します。
*楽器を自由に演奏できる
1つ目は楽器を自由に演奏できることです。
注文住宅で楽器を演奏したいという方も多いのではないでしょうか。
防音室を作ることで、周囲を気にせずに自由に楽器を演奏できます。
防音室を広さにもよりますが、サイズの大きい楽器を設置しても良いでしょう。
騒音によって近隣の方とトラブルを起こしたくないですよね。
そういった方は、防音室を検討してみましょう。
*勉強部屋としても使える
2つ目は勉強部屋としても使えることです。
防音室は室内で発生する音を外に漏らさないようにするだけでなく、住宅外からの音を遮断する効果もあります。
常に静かな空間を実現できるので、静かな空間で勉強したいという方におすすめです。
最近ではリモートワークも主流になっているので、仕事場としても活用できるでしょう。
*家族と快適に暮らせる
3つ目は家族と快適に暮らせることです。
防音室は家屋と快適に過ごす部屋としても使えます。
家族全員で音楽を聴いたり映画を鑑賞したりする方も多いです。
そのため、家族と快適に過ごせる空間を作りたいという方にも防音室はおすすめです。
□注文住宅で防音室を作る際の注意点
ここからは注文住宅に防音室を作る際の注意点について見ていきましょう。
注文住宅に防音室を作りたいという方は、間取りのプランを考える際に注意が必要です。
最初から防音室を作ることを決めている方は、防音室を中心に間取りのプランを考えましょう。
理由としては、日常生活の間取りを先に決めてしまうと、防音室を設置するスペースがなくなってしまう可能性があるからです。
注文住宅を建築すると言っても、生活に必要な間取りを考えているとスペースが足りなくなったというケースも多いです。
せっかく防音室を作っても、近隣の方とのトラブルに発展してしまうと意味がありませんよね。
そのため、防音室を作る方は、しっかりと防音効果の高い素材や窓を使いましょう。
□まとめ
今回は注文住宅に防音室を作るメリットと注意点についてご紹介しました。
注文住宅に防音室を作りたいという方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
木曽で注文住宅のプランでお悩みの方は、ぜひ当社にお問い合わせください。
無垢材を使って注文住宅で快適な暮らしを目指しましょう!
|日記
「注文住宅で無垢材を使うメリットを教えてほしい」
「無垢材と化学建材の違いについて知りたい」
注文住宅で無垢材を使おうか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、無垢材のメリットに加えて化学建材との違いについてもご紹介します。
□無垢材のメリット
まずは、無垢材のメリットについて見ていきましょう。
*経年変化を楽しめる
1つ目は経年劣化を楽しめることです。
無垢材は自然素材をそのまま使っていますので、年月がたつごとに色合いが変化していきます。
どの種類の木材を使うかによっても、色合いの変化は異なります。
自然素材ならではの色合いを楽しみたいという方は、無垢材を取り入れてみてはいかがでしょうか。
*調湿作用がある
2つ目は調湿作用があることです。
自然素材は加工されて形が変化したとしても、呼吸を繰り返しています。
そのため木材が呼吸することによって、わずかではありますが室内の湿度を調整してくれます。
*身体に優しい
3つ目は身体に優しいことです。
無垢材は木材をそのまま使用していますので、化学接着剤を使用していません。
そのため、化学接着剤から発生しやすい化学物質による影響も受けません。
小さなお子様や高齢者の方がいらっしゃる家庭では、身体への影響も気になりますよね。
そういった方は、無垢材を取り入れて安心して暮らせる住宅を目指してみてはいかがでしょうか。
□無垢材と化学建材の違い
上記では、無垢材のメリットについてご紹介しました。
では、無垢材と化学建材にはどのような違いがあるのでしょうか。
ここでは、その違いについて見ていきましょう。
上記でもお伝えしたように、無垢材は自然が生み出した建築材です。
そのため、木材が本来持っている断熱性の効果を受けやすいです。
一方で、コンクリートやビニールといった素材は、無垢材と比較して熱伝導率が約10倍もあると言われています。
つまり、それぞれを床材として比較した場合、化学建材を使うと足の温度が低下しやすいです。
快適な住宅を実現するためには、足の温度が重要であると言われています。
特に、高齢者の方はなるべく足を冷やさないようにした方が良いです。
また、無垢材は化学建材と比べて結露を防ぎやすいので、快適な環境を保ちやすいです。
□まとめ
今回は無垢材のメリットに加えて化学建材との違いについてご紹介しました。
無垢材のメリットや化学建材との違いについて理解していただけましたか。
快適な家を実現したい方は、ぜひ無垢材を検討してみてください。
木曽で注文住宅でお悩みの方は、ぜひ当社にお問い合わせください。
注文住宅を建築される方は、断熱性能について考えておきましょう!
|日記
「注文住宅を建築しようか悩んでいる」
「注文住宅の断熱性能について教えてほしい」
注文住宅の建築で断熱性能についてわからないという方も多いでしょう。
そこで今回は、注文住宅の建築を検討されている方に向けて断熱性能の重要性やおすすめの断熱材についてご紹介します。
□注文住宅における断熱性能の重要性
まずは、注文住宅における断熱性能の重要性についてご紹介します。
断熱性能が足りていないとさまざまなリスクにつながってしまうと言われています。
特筆すべきは、住宅外からの影響を受けやすいということです。
熱が伝わりやすい状態になってしまうと、冬に部屋が寒くなってしまったり、夏は部屋が暑くなってしまったりと室温が安定しにくいです。
室温の変化が大きいと、健康リスクにつながってしまうこともあります。
特に室温が低すぎると、呼吸器や心臓血管の疾患のリスクが大きくなってしまいます。
そのため、これらのリスクをなくすためにも断熱性能は重要な要素と言えます。
□注文住宅におすすめの断熱材
ここからは注文住宅におすすめの断熱材を3つご紹介します。
*グラスウール
1つ目はグラスウールです。
グラスウールは他の素材と比較して価格が安いことが特徴です。
グラスウールと性質が似ているものにロックウールという素材もあります。
ロックウールはグラスウールと比べて耐火性に優れていると言われていますが、費用はグラスウールよりも高いです。
グラスウールはガラスを、ロックウールは安山岩などの岩の繊維に加工した建材です。
これらの建材は水にあまり強くないという点だけ把握しておきましょう。
*ウッドファイバー
2つ目はウッドファイバーです。
ウッドファイバーは、カラマツやトドマツなどの針葉樹のチップを繊維化して加工した断熱材です。
断熱性に優れているのはもちろんですが、他の断熱材と比べて吸音性が高いのが特徴です。
また、蓄熱性にも優れているため、急激な熱の出入りにも対応して室内を快適環境に整えます。
*セルロースファイバー
3つ目はセルロースファイバーです。
セルロースファイバーは、新聞紙を加工して作られた断熱材です。
そして、断熱性と気密性に優れた素材であり、湿度を調整する効果もあります。
また、防虫効果があることも大きなメリットと言えるでしょう。
□まとめ
今回は注文住宅の建築を検討されている方に向けて断熱性能の重要性やおすすめの断熱材についてご紹介しました。
松本市で注文住宅についてお悩みの方は、当社にお任せください。
もちろん断熱性能や断熱材に関するご相談も承っております。
注文住宅を建てる前に流れを把握しておきましょう!
|日記
「木曽で注文住宅を建築しようと考えている」
「注文住宅を建築する際の流れを知っておきたい」
注文住宅の建築を検討されている方は、建築から完成までの流れを知っておきたいですよね。
そこで今回は、注文住宅を建築する際の流れについて解説します。
□注文住宅を建てる際の流れ
注文住宅を建築する場合、まずは土地探しと建築会社選びから始めます。
建築したい土地が見つかれば、土地の購入申請を行います。
土地の申し込みが完了すれば、注文住宅のプランを作成しましょう。
土地代と建物代を住宅ローンでまとめて考えている場合は、同時に申請を行わなければなりません。
自己資金での土地代の支払いが難しい場合は、つなぎ融資も検討してください。
注文住宅のプランを決める際は、家族全員で話し合い時間をかけて決めましょう。
プランがある程度決まれば、会社に見積もりを依頼します。
この際、どの部分にどのくらいの費用がかかっているか確認しておきましょう。
そして、工事を依頼する会社が決まれば土地の売買契約と工事請負契約を結びましょう。
その後、プランが法律に違反していないか確認してもらうことと、住宅ローンの正式な申し込みを行います。
土地購入、住宅ローンの申し込み、建設会社による契約は同時進行になりやすい傾向にあります。
ここまで完了すれば、いよいよ工事が始まります。
そして、工事が終われば住宅の引き渡しに移ります。
□注文住宅の建築で重要なポイント
ここからは注文住宅を建てる上で重要なポイントについて見ていきましょう。
*情報収集・イメージを固める
注文住宅を建てる場合、あらかじめ情報収集を行い、完成のイメージを明確に持つことが重要です。
完成イメージを明確にして会社の方に伝えることで、イメージに合わせたプランを提案してもらえます。
カタログや写真だけでイメージするのは難しいという方は、実際に建てられた住宅を参考にするのもおすすめです。
また、何よりも一番のお勧めは家族で話し合ってどんな暮らしをしたいか、夢を語ることです。
間取りばかりに目が行ってしまうと動線などがおかしくなることがあります。
どんな暮らしをしたいか根本をしっかりすることが大事です。
*予算決定・資金計画
注文住宅はプランの自由度が高い分、予算の上限を決めておくことが重要です。
予算をオーバーしないためにも、プランを決める際は家族全員で話し合い必要性や実用性をしっかりと考慮しておきましょう。
また、将来的に必要な費用も考えて予算の上限を決めましょう。
*打ち合わせ
注文住宅を建てる場合、何度も打ち合わせを行います。
その際には、どんな家を建てたいか、どんな暮らしをしたいか具体的に伝えましょう。
そして、それぞれの打ち合わせで話し合った内容は記録しておくことが大切です。
内容を記録しておくことで、次回の打ち合わせで話したいことも明確にできます。
□まとめ
今回は注文住宅を建築する際の流れについてご紹介しました。
注文住宅に関して専門家の意見を聞きたいという方は、いつでも当社にお問い合わせください。
当社の専門家が、皆様の要望をもとに全力でサポートいたします。
注文住宅の収納で失敗しないためのポイントを解説します!
|日記
「松本市で注文住宅を建てようと考えている」
「注文住宅の収納アイデアを教えてほしい」
注文住宅での生活を快適にするためにも、収納の使いやすさは重要です。
そこで今回は、注文住宅における収納アイデアに加えて収納で失敗しないためのポイントについてご紹介します。
□注文住宅でおすすめの収納アイデア
では早速、住宅内の場所別でおすすめの収納アイデアをご紹介します。
*玄関の収納
玄関の収納としておすすめなのは、シューズクローゼットです。
靴をきれいに収納しておくことで、玄関の印象も良いです。
また、クローゼットに外出用のコートを収納される方も多いです。
ここにコートを収納しておくことで、コートの相性を確認しながら靴を選べます。
また、趣味で使う道具を収納しておくこともおすすめです。
例えば、ゴルフ好きの方は重たいゴルフバッグを収納しておくことで便利に持ち運べます。
雪かきや子供の自転車等がおけるスペースがあるとなお良いです。
*キッチンの収納
キッチンの収納アイデアとして、キッチンを対面キッチンにして、壁側のスペースをすべて収納にすることが挙げられます。
キッチンでは料理に使う道具や食器など、収納物が多いですよね。
そのため、壁面をすべて収納スペースとして設けることで、家族が多い方でも使いやすい収納に仕上げられます。
*階段下の収納
階段下を収納場所として使うのもおすすめです。
階段のタイプによって異なりますが、階段下のスペースを有効活用することで、便利な収納として使えます。
使用頻度の低いものを収納しておく場所として最適と言えるでしょう。
階段下に収納を作りたい方は、間取りのプランを考える際に、業者の方に相談しておきましょう。
□収納で失敗しないためのポイント
続いて、収納で失敗しないためのポイントについてご紹介します。
注文住宅で収納スペースを作る際は、動線を考慮しておくことが重要です。
動線は住宅内で自分がどのように動くかを表したものです。
そのため、動線を考慮したうえで収納スペースを作ることで、より使いやすい収納に仕上げられます。
また、どのくらいのものをどこに収納したいか考えておくことも重要です。
長期的に住む予定の場合、家族構成やライフスタイルの変化によって収納物の量も変化していきます。
そのため、将来的な要素も考慮して収納スペースを確保しておきましょう。
□まとめ
今回は注文住宅における収納アイデアに加えて収納で失敗しないためのポイントについてご紹介しました。
注文住宅で収納に関してお悩みの方は、本記事を参考にしてください。
ご不明な点がある方は、いつでも当社にお問い合わせください。
別荘をリフォームしたい方へ!リフォームのメリットをご紹介します!
|日記
「別荘を購入しようか悩んでいる」
「所有している別荘をリフォームしたい」
別荘の購入を検討されている方や、別荘をリフォームしたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、別荘購入のメリットとともに別荘をリフォームするメリットについてもご紹介します。
□別荘購入のメリット
そもそも別荘を購入することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。
別荘を所有することの最大のメリットは、自分の理想とする環境を手に入れられることです。
皆さんも、一度は理想の暮らし方をイメージしたこともあるのではないでしょうか。
別荘では、その理想の暮らし方を実現できます。
別荘を建てる場所も、間取りのプランも自由に決めていただけます。
そのため、セカンドライフを充実させるために購入される方が多いです。
また、自然豊かな場所に別荘を購入すれば、スローライフを楽しめるでしょう。
さらに、別荘でテレワークをして働きながら休暇をとるワーケーションにもぴったりです。
□別荘をリフォームするメリット
ここからは別荘をリフォームするメリットについてご紹介します。
*愛着のある部分を残せる
1つ目は愛着のある部分を残せることです。
現在所有している別荘で、自分のお気に入りの場所やポイントがあるという方も多いでしょう。
リフォームの場合、自分が愛着のある部分は残したまま、劣化した部分を修繕できます。
しかし、建て替えの場合と比べると設計プランの自由度は低いので注意しておきましょう。
その際には、どの部分をどのようにリフォームしたいのか業者の方に相談してみましょう。
*費用が安くすむ
2つ目は費用が安くすむことです。
費用が安くすむというのは、建て替えと比較した場合のことを指しています。
一般的には別荘を建て替えるよりも、リフォームする方が費用も安いです。
しかし、リフォームのプランや規模によっては費用も大きく変化することは把握しておいてください。
*工事期間が短い
3つ目は工事期間が短いことです。
別荘の建て替えと比較した場合、リフォームの方が工事期間も短いです。
リフォームの工事が行われている際に、仮住まいを利用する場合もあるでしょう。
仮住まいを利用する場合、普段の生活よりも不自由な部分を感じることもあるはずです。
そのため、工事期間が短いことで、なるべく早く快適な生活に戻れるというメリットがあります。
□まとめ
今回は別荘購入のメリットとともに別荘をリフォームするメリットについてご紹介しました。
別荘のリフォームを検討されている方は、ぜひ一度当社にお問い合わせください。
当社では、塩尻市を中心に家づくりやリフォームに関するご相談を承っております。